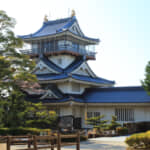小牧・長久手の戦いの「勝者」はどちらだったのか?
史記から読む徳川家康㉝
8月27日(日)放送の『どうする家康』第33回「裏切り者」では、羽柴秀吉(はしばひでよし/ムロツヨシ)に臣従するか否かで揺れる徳川家康(とくがわいえやす/松本潤)とその家臣らの様子が描かれた。徹底抗戦を訴える家臣が多数を占めるなか、老臣・石川数正(いしかわかずまさ/松重豊)は一人、秀吉の軍門に降ることを提案し続けていた。
対秀吉をめぐる徳川家家臣団の不一致

雪深い立山連峰の様子。1971(昭和46)年に開通した「立山黒部アルペンルート」は、標高3000㍍級の峰々が連なる人気の山岳観光ルートだが、越中の佐々成政は、羽柴秀吉との戦いの継続を浜松の徳川家康に訴えるべく富山からほぼ同じ道筋を踏破した。積雪の激しい道中をわずかひと月半の間に往復したことで知られ、「さらさら越え」として名高い。
長久手の戦いに勝利し、士気の高まる徳川軍だったが、戦いは、総大将に仰いだ織田信雄(おだのぶかつ/浜野謙太)が羽柴秀吉と和睦を結ぶという意外な結末を迎えた。信雄を支援する形で参戦した徳川家康にとっては、合戦を続ける大義がなくなったも同然で、兵を引くより他なかった。
和睦に伴い、秀吉は徳川家から人質を出すよう要求。さらに、公家の最高位である関白に就任するなど秀吉の勢いはますます盛んになる一方で、家康は早急の対応に迫られることとなった。
家臣一同は、秀吉に対し徹底抗戦の構えだったが、交渉役として秀吉との会見を重ねていた老臣の石川数正のみは、秀吉への臣従を訴える。数正は天下の形勢が秀吉にあることを訴えるが、家康以下、家臣一同は納得できない。
同じく老臣の酒井忠次(さかいただつぐ/大森南朋)の説得を受け、数正は家康と直接対面し、現状を訴えた。しかし、秀吉の天下を許すことのできない家康の固い決意を崩すことはできなかった。
翌日、「私はどこまでも、殿と一緒でござる」との言葉を残し、数正は妻子とともに出奔。長年仕えてきた老臣の裏切りに、家康らは呆然と立ち尽くしたのだった。
動機が明らかになっていない石川数正の出奔
織田信雄が羽柴秀吉と和睦を結んだのは、1584(天正12)年11月のことだった(『宗国史』『家忠日記』「伊木文書」)。
長久手の戦い以降、伊勢(現在の三重県東部)や尾張(現在の愛知県西半部)、美濃(現在の岐阜県南部)などで小競り合いがあったものの、羽柴軍と織田・徳川連合軍の戦いは膠着状態が続いていた。そこで、信雄が領地の安堵を担保に秀吉との単独講和へ踏み切った。条件は、秀吉に人質を差し出し、なおかつ北伊勢を除く伊勢、伊賀(現在の三重県西部)を引き渡すこと。一方、家康に提示された条件は、家康とその重臣・石川数正の実子を人質に出すことだった(『宇野主水日記』)。
これを受け、家康は同年12月12日に二男の於義丸(おぎまる/のちの結城秀康/ゆうきひでやす)を養子として秀吉のもとに送り、両軍の和睦が成立した(『家忠日記』)。
この直後となる同月25日に越中(現在の富山県)の佐々成政(さっさなりまさ)が浜松を訪れている(『家忠日記』『徳川実紀』『当代記』)。成政は、織田方として秀吉軍と戦っていたが、信雄・家康が秀吉と和睦したために孤立無援となっていた。そこで、織田方として秀吉と対峙した家康に感謝を伝えるとともに、戦闘の継続と、織田家の再興を依頼したらしい。ところが、和睦が成った直後だったこともあって、家康は丁重に断ったようだ。秀吉との全面対決を避けるという思惑があったのかもしれない。
小牧・長久手の戦いの勝敗については、さまざまな見方がある。かつては家康の勝利とする見解が多かったが、講和の条件が人質の提出、領地の割譲など片務的な内容であったことから、現在は織田・徳川連合軍側の敗北と見る向きが少なくない。
いずれにせよ、ここから秀吉と家康は武力による対立ではなく、外交戦でにらみ合うこととなる。
- 1
- 2